樫村さんへメッセージを送りましょう。
2024年12月15日 01時49分 [システム管理者]新連載について、投稿者の樫村さんへメッセージを送りましょう。
ログインし、ログイン後に表示される
(既にログイン中であれば、
メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。
ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。
連載コーナー

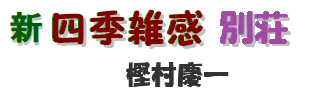 |
ログイン |
|
☞ 別巻記事 現実になりそうなUFOの話 ー 会員専用ルーム/投稿(会員限定公開)(5/27)
|
| 新 四 季 雑 感 | (32) |
樫村 慶一
96歳のある男性の人間像
私は1930年、つまり昭和5年生まれで、早生まれだから2026年の4月1日で満96歳になる。現在住んでいるのは、練馬区にある地元の人が始めた、個人経営の終身型老人ホテル(と称している)である。ホテルというだけあって、普通の老人施設にある、”制限””制約”と言うものが一切ない。食事時間はもとより、連れ込みOK、ペットOK、門限なんて勿論ない、風呂だって常識的時間(午後11時頃まで)ならOKだし、気楽で快適だ。いわゆる老人ホームにはいっている同年代の友人が何人かいるが、彼等の話しと全く違う。それでいて、介護サービスもしっかりやってくれる。だから天国なのだ。
入居者は部屋数が全部で43の内、男は3人、40人はお婆さんである。有名人も何人かいる。多少はお婆さんと呼ぶのは可哀そうな人もいるが。しかしながら、此処に往診してくる医者に、私は「奇跡的人間」だと言われた。95,6歳の男で月10日も出歩いているのは、奇跡的人間なんだそうだ。その奇跡的な人間は、今年午歳の年男である。午と牛の文字の違いは、姿形をそのまま表している。牛に角がないのが午だ。
話しは飛躍的に5500万年遡る。上野の科学博物館で「大絶滅展」と言うのをやっている。6600万年前に直径約10キロの隕石がメキシコに落ち、その爆発で灰が地表を覆い、日照がさえぎられて、動植物が大量に絶滅した。恐竜が絶滅しだのものこの時だ。それから1000万年後に馬の祖先が現れたという。始めは今の普通の犬くらいの大きさだったのが、段々進化して大きくなったそうである。特に特徴は足だ。始めは蹄は3つに分かれていた。当時は植物が繁茂し始め、また大草原が現れて、遠くから天敵に狙われるようになった。そのため、高速で走れるように、複数の蹄は進化して一本になった。これにより時速50 キロくらいまで走れるようになったという。
|
|
私は、今まで外で何か催しがあると、つねに何かやらされた。乾杯の音頭とか、締めの挨拶とかである。ところが此処へ来て年上がゴロゴロしているのを見て、やれやれとほっとしたものである、ただし、先にも書いたが、婆さんばかりで、つくずく女性の強さ、丈夫さを知った。
政府発表の日本人の老齢の男女比は82対18だ。それをここに当てはめると、婆さん36人対爺さん7人が適正数になる勘定である。しかし男は3人しかいない、しかも3人の内一人は脳梗塞の後遺症で半人前だし、もう一人はテレビもない部屋からほとんど出て来ない。結局普通に動いている男は私だけということになる。だから目立ってしようがない。
人によく、95歳まで生きるコツは何か?と聞かれる、しかし95歳は他にもたくさんいるだろうし、皆それぞれが違った人生を送ってきているのだから、そんなことを私に聞いたって、役に立つわけないだろうと思う。さらには、最近6、70代の医者がやたらに本を書く、和田秀樹医師などは、もうすっかり作家気取りだ。私は、極めて疑問に思うのだが、60代70代がなんで、90、100歳までいきる術がわかるのかと。幾ら医者だって先行きの見通しなんて、個人の肉体的条件を始め生活実態が違うんだから、分かる筈がないだろうと思うのだが、やはり若い人は、何か魔術書とでも思うのだろうか? ここに老人3原則と言う格言がある(註1)。少なくとも、これは本質をついている。覚えておいて損はない。
そこで、95歳、間もなく96歳になる人間の実態はどんなものなのか、つまらない本を買わなくてもいいように、私の実像を自分で暴いてみようと思った。役に立たなくても読み賃はいらないから安心で頂きたい。
『95歳の(間もなく96歳になる)健常と言われる男の人間像』
| 健康全般 |
軽い腰痛があるが外出には支障なし。 12345678901234567890123456 |
| 精神面 |
時々安定剤が欲しくなる。 12345678901234567890123456 |
| 脳細胞 |
直前(数秒~1H以内)の物忘れが多くなった。 12345678901234567890123456 |
| 毛髪等 |
普通に生えている。但し白毛6分。 12345678901234567890123456 |
| 肺 |
昨年6月肺がんCT検査、異常なし。 12345678901234567890123456 |
| 血管 |
首及びその他の動脈硬化進行中。 12345678901234567890123456 |
| 内臓 |
年に1度、胃カメラと肝臓から前立腺 12345678901234567890123456 |
| 手足 |
足が細くなり弱った、まだ両足だけで立てる。 12345678901234567890123456 |
| 眼、耳 |
目は昨年11月定期検査、 12345678901234567890123456 |
| 食事 |
食事の量はかなり減った、また食欲も落ちた。 12345678901234567890123456 |
| 運動 |
マッサージ師に教えられたストレッチを朝晩している。 12345678901234567890123456 |
| 睡眠 |
睡眠導入剤を1錠服用、7時間は眠る。 12345678901234567890123456 |
| 風呂 |
これが問題、月に精々10回程度になった、 12345678901234567890123456 |
| 掃除ごみ捨て |
特に問題なし。 12345678901234567890123456 |
| パソコン |
ないと人世の終わりと感じるかもしれない。 12345678901234567890123456 |
| 携帯電話 |
固定電話の代わりであり、 12345678901234567890123456 |
| 大学 |
25年度で8年目、 12345678901234567890123456 |
| 友人付き合い |
ほどほどにある。 12345678901234567890123456 |
| 外出 |
上記の付き合いのため、及び映画を見に出かける。 12345678901234567890123456 |
| 読書・新聞 |
宇宙物が好み。 12345678901234567890123456 |
| テレビ |
そこそこに見ている、 12345678901234567890123456 |
| その他 |
殆ど毎晩、夕食のトレイに、 12345678901234567890123456 |
| 先行きの見通し |
健康状態は分からない。 12345678901234567890123456 |
| マンション処分 |
未定。 12345678901234567890123456 |
| 月々の支払 |
負担にはなっていない。 12345678901234567890123456 |
| 過去への思い |
懐かしいことばかり、妻が健康な頃が特に。 12345678901234567890123456 |
(註1) ①風邪ひくな ②転ぶな ③義理を欠け。
(註2) 愛知県の知多半島にある野田の大坊と言うお寺の住職。すでに故人。
以上
(2026.1.5 記)
いいね!ボタン
メッセージもよろしく
☞ ログインボタンをクリックすると
新しいウィンドウでログイン画面が
小さく表示されます。
ログイン後、ページの右端にある (リロードボタン)をクリックすると、
ログイン状態の表示になります。
新連載について、投稿者の樫村さんへメッセージを送りましょう。
ログインし、ログイン後に表示される
(既にログイン中であれば、
メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。
ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。
新連載について、投稿者の樫村さんへメッセージを送りましょう。
ログインし、ログイン後に表示される
(既にログイン中であれば、
メッセージに対するコメントや返事は、表題をクリックすると表示されます。
ログインせずに上の★星マークの「いいね!」ボタンをクリックするだけでも構いません。